本業である税理士業で、若い時はいろいろな失敗をしました。
今はその失敗が糧となっているわけですが、その中でも思い出深いのが、譲渡所得の添付書類についてです。
この失敗以降、私自身が譲渡所得の申告をする時には、いろいろと工夫をするようになりました。
今回は譲渡所得の添付書類について考えてみたいと思います。
※守秘義務の関係で事実関係は変更しています。

※長女と公園にて。
添付書類は必須ではない
そもそも論ですが、譲渡所得の特例(居住用の3,000万円特別控除など)を受けない場合には、添付書類は不要とされています。
ですから登記事項証明書や売買契約書を付ける義務はないわけです。
ただ、特例を受けない場合でも、最低限、譲渡所得の内訳書は付けなければいけません。
※これがないと譲渡所得の計算過程が分かりませんからね。
――
売買契約書や登記事項証明書を添付しないと…
「付けなくていい」と言ってはいますが、ほとんどの税理士は売買契約書や登記事項証明書を付けていると思います。というのも、付けないと税務調査の確率が高まるからです。
相当昔の話で、私がまだ駆け出しの頃ですが、高額な不動産(賃貸ビル)を個人で売却したお客様がいて、その譲渡所得の申告を任されました。
その申告書を税務署に提出する時に、なぜか私は売買契約書や登記事項証明書を付けなかったんですね。
そうしたところ、申告から数か月後に税務署から電話が入りました。
「〇〇税務署ですが、納税者である△△様の税務調査に伺いたいのですが。」
私はドキリとしました。なぜ税務調査に来るのか尋ねたところ、
「売買契約書が付いていなかったので税務調査に伺うことにしました。」
というのです。私は「今から売買契約書を送りますから税務調査を見送ってください!」とお願いしたのですが、
「もう決定したことなので、だめです〜(^^ )」
と半分笑いながらの調査官の声が、電話口から流れてきたのを思い出します。
売買契約書は、売買金額を裏付けるほぼ唯一の書類と言っていいでしょうから、税務署は必ず確認するでしょう。
また、登記事項証明書は、誰に所有権が移転したのかが分かる公的書類なので、こちらも税務署は必ず確認するはずです。
さらには仲介手数料の領収書も確認します。売主が払った仲介手数料は仲介会社の収入に計上されていなければおかしいですよね。ですから、その不動産会社への調査にも使われていると聞きます。
譲渡所得の申告書は、調査官が税務調査へ行くための、いわば「飯の種」とも言うべきものです。
ですから、必要な資料を順番どおりに添付していくのが大切です。私の場合、
「売買契約書 → 購入時の資料 → 経費資料 → 登記事項証明書 → 特殊な添付書類」
という並びで、譲渡所得の内訳書にあるとおり「収入 → 取得費 → 経費」という流れに合わせて添付資料を付けていくようにしています。
こうすることで、調査官も資料を見た時に「きちんと整理され、流れどおりになっているな」ということで調査省略、という風になっていくのではないか、と個人的に思っています。
また資料が多い場合は、最初に「添付資料一覧表」なるものを付けて、どのような資料を付けているかをあらかじめ記載しておくと、さらに印象がいいでしょう。
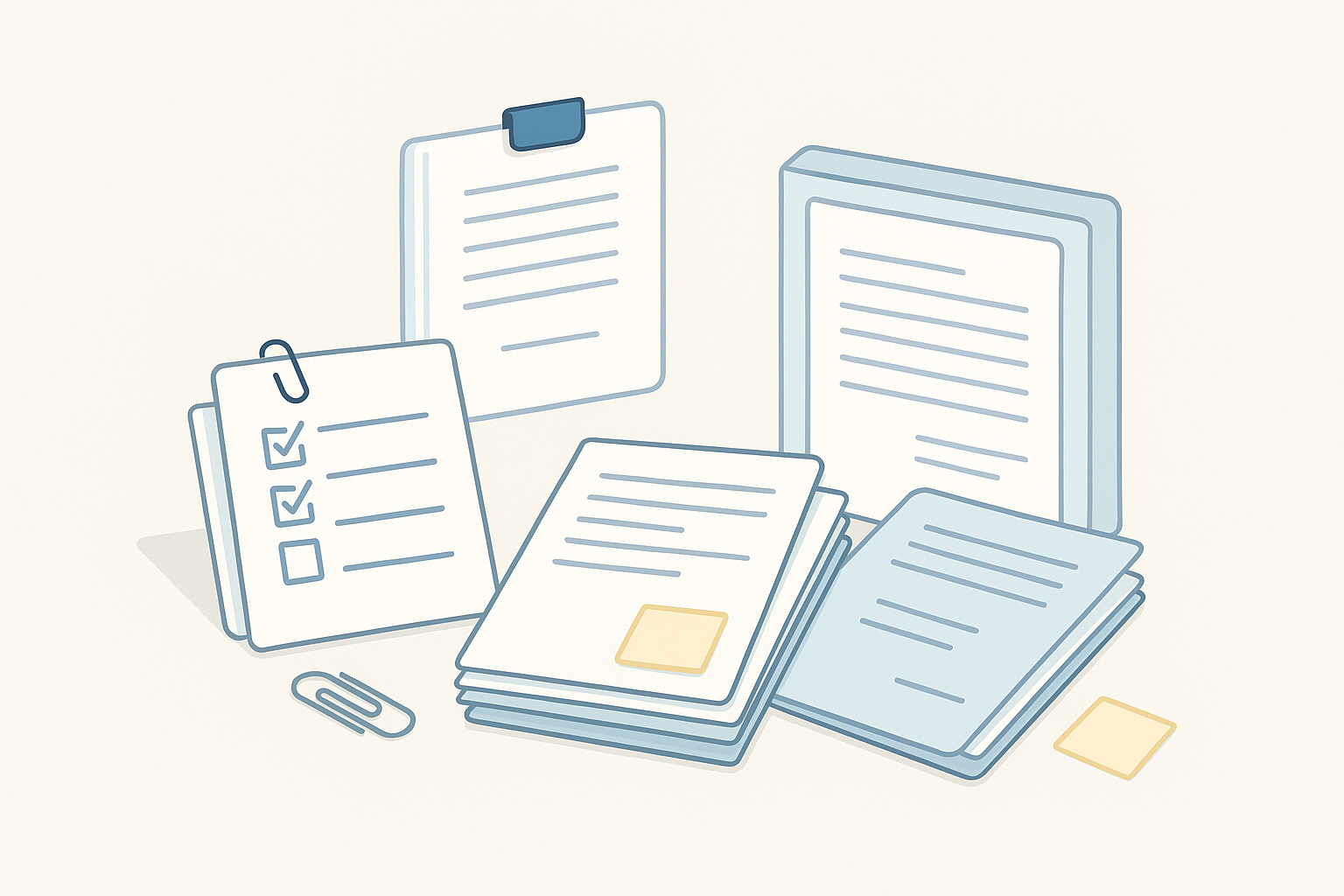
――
「事情説明書」にこだわる
特殊な事情がある場合には「事情説明書」を付けるべきです。
「事情説明書」なる文書は、私が勝手に名付けているもので、人によっては「上申書」だったり「申述書」だったりしますが、要は特殊な事情を役所に対して詳細に説明する文章、ということになります。
私が事情説明書を付けた方がよいと思うのは、例えば次のような場合です。
・取得費の推定計算をする場合
・複雑な取得費計算をした場合(取得費を借地権部分と底地部分に分けて計算する、売却直前に増改築がある、等)
・住民票と実際の住所が異なる場合(居住用特例を受ける場合)
・登記上の所有者と実際の所有者が異なる場合
他にもいろいろあるのでしょうが、一番よく使われているのは「取得費の推定計算をする場合」だと思います。
最近、同業の税理士先生や不動産業者様から、取得費の推定計算についてご相談をいただく機会が多いのですが、この場合は事情説明書を付けないと、税務署から多分電話がかかってきますよね。私は何か特殊な事情がある場合には、積極的に事情説明書を付けています。そうすることで税務署も余計な税務調査に行かずに済み、納税者の方も税務調査の負担を受けない、という双方にとっての win-win になりますからね。
――
事情説明書で気をつけている点
事情説明書に決まったフォーマットはありませんから、自由に書けばいいのですが、そうは言っても書き方が分からないという税理士先生もいらっしゃるでしょう。私が参考にしているのは以下の書籍です。
弁護士先生向けの書籍なので、譲渡所得の申告に直接使えるような表現にはなっていません。
ただ、弁護士先生が裁判所や紛争先に出す文書について解説している本なので、「相手に事実をきちんと伝える」という意味ではとても参考になります。
それらを踏まえて私が意識しているのは次のようなことです。
・時系列で箇条書きにする
まずは事実を税務署に伝えなければなりません。それもできるだけ分かりやすく。そこで「〇年〇月 … Aが売却不動産を購入」のように、購入から売却までの流れを上から下へ、時系列で書くのが一番わかりやすいのではないでしょうか。
・特例の条文番号や通達番号を書く
事情説明書には、該当する条文番号や通達番号を記載します。税務署員も「きちんと条文に当たって調べているんだな」と理解していただけると思います。
・裁決例などを添える
さらに込み入った事案で解釈に悩むような時は、具体的な判例や裁決例を記載し、「こちらに該当すると考えますのでご確認ください」といった趣旨を、もう少しきちんとした形で記載するようにしています。税務署には判例や裁決例を調べるデータベースがあると聞きます。難しい案件であれば職員もそこで調べるでしょうから、先回りして根拠を示しておけば、印象は相当よいのではないでしょうか。
――
譲渡所得の申告は、既存のお客様以外からお受けすることもあります。
その場合、お客様の事情や背景をすべて1からヒアリングすることになりますから、一発勝負になり、本当に気を使います。
最近多いのは「取得費がわからない」というご相談です。数十年前の購入時の売買契約書なんて、普通、保存していないですもんね。
若い税理士先生は、私のようにならず、譲渡所得の申告書には最低限、売買契約書と登記事項証明書を付ける――この基本だけはぜひ徹底していただきたいものです。
