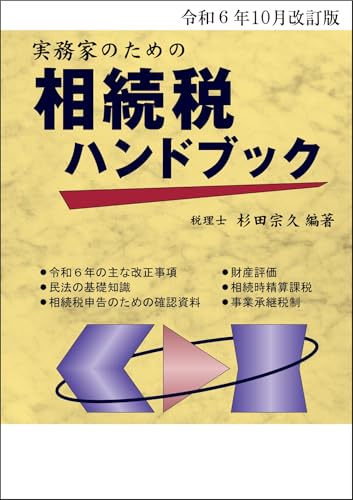私が独立開業してから、十数年が経ちました。
開業当初から毎年のように「税務ハンドブック」を購入しています。
この税務ハンドブック。
かつては「肌身離さず」といってよいほど持ち歩いていたのですが、気がつけば最近はカバンに入れる機会が減ってきました。
今回は、その理由と、今でも「やっぱり持っていて良かった」と感じる体験談を整理してみたいと思います。
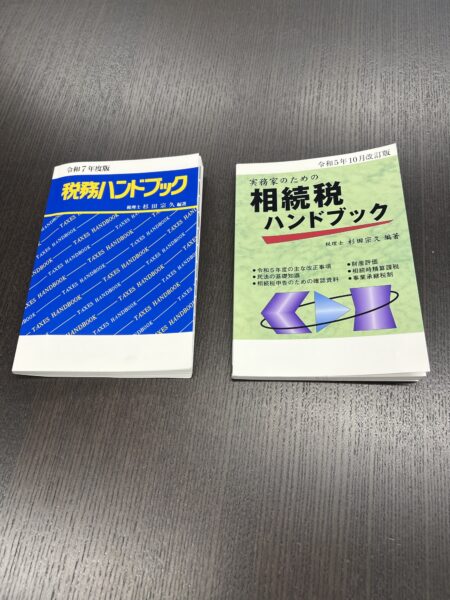
税務ハンドブックとは
税務ハンドブックには、法人税・所得税・消費税・相続税といった主要な税目に加え、印紙税や登録免許税の税率まで一通り載っています。
例えば顧問先の社長様とお会いした時、ふいに税率や要件を聞かれることがあります。
そんな時、ハンドブックを取り出し、パッと開いて「ここに載っています」と答える。
それだけで相談者様も安心されますし、自分自身の心強いお守りにもなっていました。
開業当初は「みんな持っていた」
今から10年ほど前でしょうか。
地元の税理士が集まる会合に出席したとき、「税務ハンドブックって持ってます?」という話題になったことがあります。
すると10人、20人と集まった中で「私も持っています」「私も」という声が次々と。
当時はかなりの割合でカバンに入れている先生が多かったように思います。
私も例外ではなく、外出の際は必ず持ち歩いていました。
重いのですが、それでも「これがないと不安」という存在だったのです。
持ち歩かなくなった理由
そんな必需品だった税務ハンドブックを、最近は持ち歩かなくなった。
その理由はいくつかあります。
1. スマホとネット環境の普及
昔はネットで税務情報を探そうにも、十分な情報が出てこなかったり、公的機関のサイトが整っていなかったりしました。
しかし今では、国税庁のホームページも充実し、検索すれば信頼できる情報にすぐたどり着けます。
外出先であってもスマホさえあれば、ほとんどのことは調べられるようになりました。
2. 外出の機会そのものが減った
Zoomをはじめとするオンライン面談が普及し、コロナ禍を経て対面の場面は大きく減りました。
顧問先や、知り合いの税理士先生からの相談も、資料は事前にデータで送っていただき、画面共有で確認する。
そういうスタイルが定着してからは、そもそも「現場に持って行く」という必要が少なくなったのです。
3. 自分自身の経験値が増えた
開業して十数年。
相続税、譲渡所得、法人の決算…いろいろな案件を経験してきました。
最初は何でも「本を開かないと不安」でしたが、今では大抵のことは頭の中に入っていて、その場で説明できるようになりました。
もちろん細かい確認は必要ですが、「ハンドブックがないと答えられない」という場面は減ってきました。
それでも「持っていて助かった」体験談
では、もう完全に不要になったかといえば、そうでもありません。
実務の中で「やっぱり持っていてよかった」と思う場面がいくつもありました。
不動産売買の決済現場
ある時、不動産の決済に立ち会った際のことです。
売買契約書に貼る印紙税の金額が微妙なラインで、「どちらになるのか」と先方の不動産業者さんに尋ねられました。
その場で税務ハンドブックを開き、「ここにこのように書いてあります」と示すと、すぐに納得していただけました。
紙の本を直接見せることで、相手も安心される。
この「信頼感」は、スマホ検索ではなかなか得られないものだと思います。
銀行での金利交渉
別の場面では、顧問先のオーナー様と一緒に銀行へ伺った時のこと。
借入金の金利が高く、交渉の余地があるかどうかという相談でした。
その時、税務ハンドブックに載っている「相続税延納の利率」を開いて銀行の担当者に示しました。
「相続税を分割払いしても、この利率なんですよ。御行の金利、ちょっと高すぎませんか?」と。
すると担当者が「なるほど、それは検討させてください。ちょっとその部分のコピーをとらせてもらっていいですか?」と、コピーをとられました。
結果的に金利が下がったのです。
この時も「紙に書いてある数字を見せる」ということの説得力を強く感じました。

※外出先での風景
相続税ハンドブックは今でも必携
ちなみに「相続税ハンドブック」は今でも毎年購入しています。
相続税は論点が幅広く、細かい要件確認も多いので、やはり一冊にまとまっていると安心です。
特に、相続の初回相談の場では、お客様も不安を抱えていらっしゃいます。
その場で相続税ハンドブックを開き、正確に確認しながら説明することで、信頼していただける。
そういう意味では、今も大切な相棒です。
まとめ
普段は持ち歩かなくなった税務ハンドブックですが、ここぞという時には今でも力を発揮してくれます。
時代はデジタル化が進み、紙の需要は減り続けるのでしょう。
それでも「信用力」の点で、書籍という形は最後まで残るのではないか。
私はそう思っています。