以前、借地権について次のような記事を書きました。
普通に生活している方は「借地権」という言葉を耳にしたことはあっても、自分の暮らしの中で借地権と接点があることは、まずないと思います。ところが、地主様や不動産オーナー様のお手伝いをしていると、この“借地権”が現場ではちょいちょい顔を出します。
税理士はとかく評価(いくらで評価するか)に目が行きがちですが、それよりも先に、その資産としての性格をきちんと理解しておくべきだと感じています。
特に、借地権者(借りている側)の視点と、借地権設定者=地主様(貸している側)の視点、その両方からアドバイスできるように、最低限の知識と感覚は持っておきたいところです。
私のお客様は地主様や不動産オーナー様が多いので、どちらかと言えば借地権設定者(地主)側のご相談が中心です。
ただ、その逆で、借地権者側のお客様も少数ながらいらっしゃいます。
そうした方々と長くお付き合いを続けていると、借地権者がどんな生活を送り、どんな事業形態で、どんなことに困りやすいのか――その輪郭が少しずつ見えてきます。今回は、私が現場で借地権に接してきて感じたことを、経験ベースでまとめてみます。

なぜ居住用が多いのか
まず、借地権は居住用が圧倒的に多い、という実感があります。もちろん、店舗用や倉庫用など事業目的の借地も存在はしますが、件数で言えば居住用が大半でしょう。明治から昭和にかけて工業化が進み、農村部から都市へと人が流入したとき、地主から土地を借り、建物は自分で建てるという住まい方が広がりました。
度重なる法改正の中で借地人の権利が徐々に強くなっていった歴史も相まって、結果として、今日に至るまで居住目的の借地権が多く残っているのだと思います。
借地権はどこに多い?
そして、居住用が多いということは、借地権は住宅地に多い、ということでもあります。地価が極端に低い地域では土地を買ってしまうことが現実的ですから、そもそも借地権に市場価格がつきにくい。必然的に、ある程度の都市部で、かつ住宅地に借地権が集まります。感覚的には、新宿から西のエリアや、隅田川を挟んだ東側のエリアなど、まとまって見受けられる地域があるように思います(もちろん個別の事情によります)。
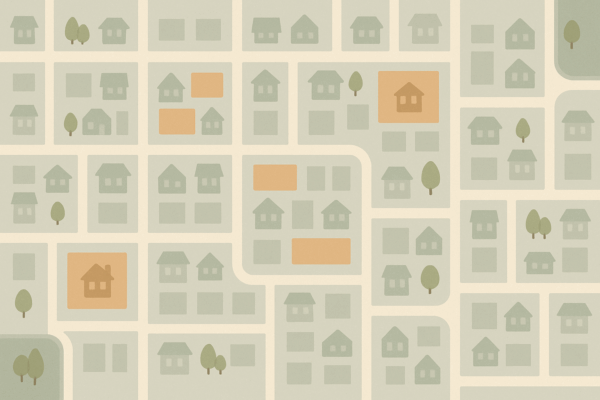
用途変更は要注意(承諾と契約)
借地契約書には利用目的がきちんと書かれています。居住用で契約しているのに、勝手に店舗利用に切り替えると、契約違反として解除のリスクが生じます。用途変更には、原則として地主様の承諾や契約変更が必要です。ここは軽視しない方がいいですね。
底地を買い取ってほしい本音と現実
次に、地主側の本音と現実です。相続を機に、面倒な権利関係を整理したい――つまり底地を借地人に買い取ってもらいたい、と考える地主様は少なくありません。
ただ、借地人側が買い取れない、という現実に直面することが多いのも事実です。借地にお住まいの方は、普通のサラリーマンや個人事業主、あるいはリタイアされたご高齢の方が中心ですから、数千万円単位の資金を用意するのは容易ではありません。銀行融資がなかなか下りない、という壁もあります。
さらに、長年の慣行で地代が比較的低廉なケースでは、「このまま借り続ける方が得」という合理的な判断も働きます。そうなると、借地関係はそのまま長く存続しがちです。
借地人は高齢化の傾向、動きづらさの理由
借地権者の世代構成にも特徴があります。体感では、ご高齢の方が多い。お子さんはそれぞれ賃貸や分譲マンションに住み、古い実家にはおじいちゃん・おばあちゃんだけ、という構図です。
現実的には、相続の発生を契機に権利整理の話が動くのが理想ですが、それが数年後なのか数十年後なのかは誰にも読めません。結果として、双方ともに“待ち”の時間が長くなります。
底地の所有者の属性
地主様の属性は、先祖代々の承継がやはり多い印象です。中には、底地を新規に購入して不動産投資として保有する新オーナーもいらっしゃいますが、多くありません。底地はキャッシュフローが薄く、借地権者の同意なしに自由度に活用するのが難しい資産だからです。
それでも旧法が残るわけ
ここで、旧法の借地権の話にも触れておきます。
理屈の上では、借地人が底地を買い取る、地主が借地権を買い取る、あるいは双方が共同で第三者に一体売却する――こうした動きが進めば、権利は完全な所有権に統合され、借地権は消えていくはずです。
ところが現場感覚では、旧法の借地権が思ったほど減っていません。
居住用では売買の理由が生まれにくいこと(相続や転勤など特別な事情が必要)、資金調達や融資のハードル、地代の低さから“現状維持が合理的”になってしまい、動きにくい資産として長期に残存しているのだと感じます。
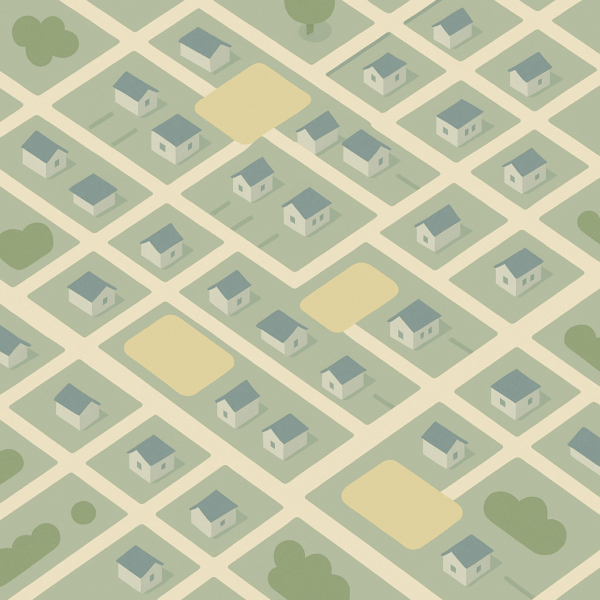
交渉が止まりやすいポイント
不動産会社にご一緒する場面では、借地権と底地の「停滞感」を肌で感じます。地主様は売りたい、でも借地人は買い取れない。理由は、単にお金がないという以上に、銀行が融資を出しづらい、今の地代で借り続ける方が合理的、といった現実的な事情が複数絡みます。
交渉は、最初に切り出した側が不利になりがちで、どちらも様子見に入る。そうなると、地主様はストレスが溜まり、その愚痴が税理士に届く――そして私はまた一つ勉強させていただく、という循環です(^^ )。
多くの方にとって、借地権は縁遠いテーマかもしれません。ただ、もし相続した財産の中に借地権があった場合、あるいは逆に底地が含まれていた場合は、少し立ち止まって考えてみる価値があります。
数字だけでなく、誰が、どの時点で、どの程度の自由度を欲しているのか。暮らしと数字を両方見ながら、相手方の事情も想像しつつ、現実的な落としどころを探る――借地権は、そのような資産だと感じています。
